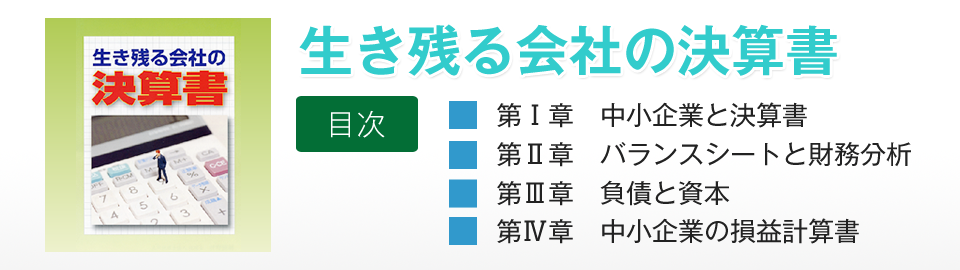
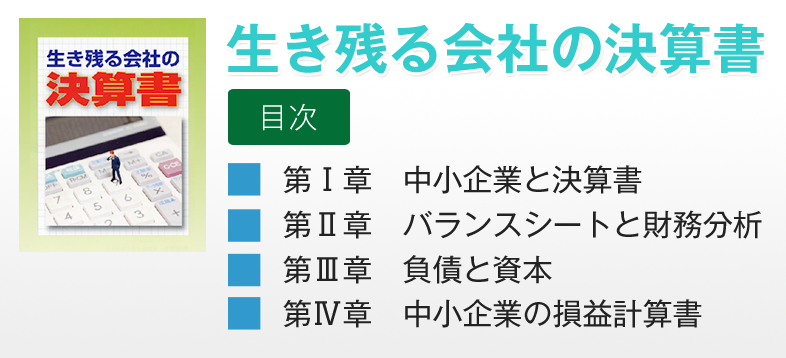
決算書に仮払金や立替金や貸付金があるときは、まず回収に問題がある不良債権と考えてよいでしょう。
まず、仮払金というのは、通常は費用の未精算であり旅費の仮払金などが典型ですが、この金額が大きかったり、数期にまたがっているのであればまず回収できない不良債権なのです。仮払金は、常に精算を心がけなければならないのですから、こういう勘定科目が決算書に残っていること自体問題なのです。
さて、債務超過とともに、金融機関から指摘を受けるのは、会社から社長への貸付金です。とくに金融機関から、お金を借りている身でありながら、その資金が流出しているわけですから、金融機関がその理由を糺すのは至極もっともなことなのです。この貸付金は、返済がされていませんと、金融機関は「含み損」として評価しなければなりませんので、金融機関も「とにかく昨年の貸付金よりは減らして下さい」と改善を要求してきます。 担当者も一気に解決できないのはわかっています。
対策方法は2つあり、別に機会を設けて説明しますが、手間も時間もかかります。
ダンゴ3兄弟の3番目は立替金あるいは未収金で、たいては、社長に対する債権になっていることが多く、数年のわたり変化がないものは不良債権と考えなくてはなりません。
中小企業の決算書の仮払金、立替金、貸付金のダンゴ3兄弟は、ほとんどの場合問題があるものと考えられます
わが国の掛売上の商慣習は、江戸元禄期の西暦1700年にはすでに確立されていました。井原西鶴の「世間胸算用」では、大晦日の支払を巡る20の短編が書かれていますが、暉峻康隆氏によれば、大晦日の他「旧七月の盆節季を上半期の支払い日とし、その合間に「中払い」と称し、三月、五月、九月の節句の前日」に支払う慣習があったようです。この帳面による掛け売り・掛け買いの商慣習は現代まで続いておりまして、書面や口頭で締めと支払の日が定められて商談がスタートするのです。
この支払の条件が、常に守られている会社もあれば、まったくルーズな会社もあったりしますが、決算書をみて「売掛金+受取手形」これを売上債権といいます、と月商と比較すれば、貴社の売上債権の残高が正常であるかどうか判断することができます。
ちなみに貴社の決算日の売上債権は月商の何ヶ月分になっているでしょうか。
分子の売掛金には、消費税が含まれています。分母の売上には、経理方法によって消費税が税込のこともあれば、税抜のこともあります。比較するのですから税込の月商とするのがよいでしょう。
この率は、売上債権回転期間とよばれます。「分析統計」によれば、全産業平均は、1.69ヶ月です。業種別にみますと、建設業53,155社の平均は、1.52ヶ月、卸売業21,376社の平均は2.12ヶ月となっています。製造業が比較的長く、17,784社の平均は2.34ヶ月となっています。
この期間が2.5ヶ月より長いのは感心できません。長いのであれば、不良債権が多くなっているのか、あるいは、粉飾決算をしているのか、どちらかなのです。
社長さんの中には、業界の特殊性を強調する方もいらっしゃいます。つまり業界によっては回収サイトが2.5ヶ月よりも長いのが普通であるという言い分です。
残念ながら、金融機関はそれぞれの業界の個別事情を理解しているわけではありませんし、また、そういう会社に限って預金残高が1ヶ月もなく、資金繰りが逼迫していることが多いのです。ですから、売上債権回転期間は、2.5ヶ月以内が正常値であると私は断定します。
「掛かるもの」の費用はどうしても掛かる費用で、固定費と言われます。人件費・物件費が代表的なものです。これ対して「掛けるもの」は、あることのために費用を掛けるという意味ですから、戦略的な費用である「広告宣伝費」や、従業員の福利厚生を高める「福利厚生費」得意先開拓のための「接待交際費」などがあります。
なお、役員給与は、オーナー企業であれば経営者の利益を先取りしているわけですから、ここでは除外して考えます。
こうして考えてみますと、費用は3つのグループに別けられます。
多くの小規模の会社では、販売費および一般管理費のほとんどが、人件費と物件費となっている筈です。
私は平均給与の450万円を上回る役員給与には返済能力があるものと考えますから、この場合、役員給与は450万円以下であれば、ぎりぎりで経営しているわけです。
また、役員給与が450万円以上であれば、その分が支払余力であるものと考えます。
役員給与が相当大きい場合で、他の掛ける費用が少ない場合は、本業が健全なしまりやの社長です。
成長期の企業であれば、税金を払うよりは、経費を掛けてゆきたいとおおよその社長さんは考えますから、掛ける経費が大きくなります。将来の投資と考えるわけです。
こういう会社では、役員給与はもちろん450万円より相当に大きいのが普通です。
こうしてみてゆきますと、販売費および一般管理費の勘定科目を眺めただけで、ギリギリの会社、しまりやの会社、戦略的な会社の3つのタイプに別けることができます。
営業利益や経常利益などの差し引き計算された利益を眺めただけでは、どういう会社なのかイメージがつかめません。
役員給与の多寡と、戦略的な掛ける経費があるかどうかを観察すれば、会社の経営のイメージが掴めるものなのです。
会社間の取引で、得意先に対して売上債権(売掛金と受取手形)があれば、再建中など余程の事情がない限り、仕入先に対して仕入債務(買掛金や支払手形)があります。
そして、契約や商慣行で、得意先との間で入金サイトが、仕入先との間で、支払サイトが決まっています。 この入金サイトと、支払サイトだいたいにおいて長い業界ではともに長く、短い業界ではともに短いものです。 商売は、共存共栄で成立するのですから、先方が入金済みなら支払ってくれてもよさそうだと思うのです。
仕入債務が、月商に対して、どれくらいになっているでしょうか。
「分析統計」では、117,408社の平均は、1.15ヶ月です。各業界の平均値は次のとおりですが、月商の1.5ヶ月以内が目安ではないでしょうか。 「分析統計」では、買入債務という用語になっています。決算日現在、買掛金や支払手形は、商品代金の未払の代金です。在庫になって残っている商品もあるでしょうし、あるいは販売されて売上債権になっているかもしれません。
けれども、棚卸資産回転期間(T)と仕入債務回転期間(S)は、卸売業を除いて、相当に近似します。
1.03-1.15(全産業)、1.42-1.53(製造業)、0.92-0.80(小売業)、0.35-0.54(サービス業)、1.12-1.52(建設業)となり、最大の開きでも0.4ヶ月しかありません。卸売業は、さすがに在庫は0.85ヶ月・仕入債務は1.75ヶ月と、商品はすぐに回転しています。 つまり、大局的には、簿記の(商品)xx(買掛金)xxという仕訳のとおり、支払いが残っている買掛金や支払手形にみあう在庫が会社に残っているということです。
◎ポイント □ 仕入債務は、月商の1.5ヶ月以内が目安
決算日の現金残高、この数字がしっかりしていれば、およそ几帳面に経理されていると考えられますし、この数字が、取引規模に比して大きいのであれば、およそ経理はアバウトになされていると考えざるを得ません。
中小企業では、外部の監査はありませんし、現金出納帳自体がなかったりするのですから、現金残高はかなりいいかげんであったりするのです。
現金残高は、会社にある現金ですが、同族会社では、すぐに社長が用意できる残高までが、正常でしょう。したがって、役員給与の2ヶ月分位、50万円であれば、100万円がせいぜいで、それを超える金額は役員に対する貸し借りなのです。
現金残高が、社長がすぐに用意できる範囲、役員給与の2ヶ月分相当額を超えるようになりますと、事実上、その超える部分は、社長への貸付金ということになります。
社長への貸付金は、社長の持ち出し分ですから、実際は資本金を食っていることになり、金融機関は感心しません。
要するに、金融機関は、現金残高が大きすぎても、あるいは、社長への貸付金になっていたとしても、どちらも感心しませんから、そういう状況から早いうちに脱却しなければなりません。
減価償却が、適正に規則的にされているかどうかは、金融機関の関心事です。
減価償却がしていなかったり、部分的な償却に留まっていますと、正確な減価償却費との差額がどれくらいなのか、の問い合わせがしばしばされます。
もし正規に減価償却をしていたら、膨大な赤字決算になっています。それを避けるために減価償却をしていなかったり、部分的な減価償却に留まっているわけです。
中小企業では、公認会計士の監査がありませんから、減価償却がいいかげんになっていることがしばしばです。
そこで、なぜ減価償却が重要なのかといえば、借入金を返済できる会社の能力である返済可能利益に関係があるからです。
税引後当期純利益に減価償却費を足した金額が返済可能利益なのです。
償却費は資金の支払がない費用なので、減価償却前の利益が、年間の借入返済額を上回れば、返済を続けていくことができます。
つまり、「減価償却前当期純利益>借入返済額」であれば、返済能力があるとみることができるのです。
損益計算書で、まず金融機関がチェックするのは減価償却をしているかどうかなのです。
流動負債は、買入債務である支払手形や買掛金のほか、1年以内に支払わなくてはならない、未払金、短期借入金、そして税金です。
この支払財源は、現在ある現金預金と、回収の見込みがある売上債権、つまり売掛金、受取手形が充てられます。現金に換金でき、すぐに支払に充てられる現金預金および売上債権を当座資産と呼んでいます。
流動資産を当座資産で割った値を、当座比率といいますが、この比率は100%以上が好ましいとされています
ちなみに、帝国データバンクの分析統計の全産業117,408社の当座比率は、166%という数値です。しかしながら、売上債権の中に回収の見込みがない不良債権があるとき、あるいは、粉飾決算の場合、この数値が大きくなる傾向があります。
手元流動性が1カ月以上、つまり現金預金が月商分以上ある会社は問題がありませんが、現金預金がそれより少ない会社では、この数値の信憑性を確保するためには、月商の2.5カ月を超える売上債権はカットして再計算するのがよいでしょう。そうすることにより、不良債権や粉飾による歪みを除いてこの数値を計算することができます。
製造業や卸売業のように、得意先との取引に継続性がある場合、決算書の売掛金の得意先は、昨年と今年でかなり同じ顔ぶれになっています。
税務署に提出する決算書には、売掛金の内訳書がありますから、昨年と今年を比較してみてみましょう。ちなみに、甲社の売掛金残高は次の表のようになっています。
A物産・B商事・D企画ともに長い取引がある得意先です。
C興産は急激に残高が増え、Eセンターは新規の得意先であることがわかります。クレームやトラブル、得意先の資金繰りの悪化等で入金が遅れていることはないでしょうか。また、X産業とY製作所は残高が変化していません。こういう場合金融機関は、1年間あるいはそれ以前から回収されていない可能性があるものとして、不良債権の査定損を計上することがあります。
次に量的な観察です。昨年度末の売掛金は4,821,600円です。月商で割って売上債権回転期間をみると2.38ヶ月でした。今年は、売上こそ昨年対比5%の伸びでしたが、売掛金は3,121,650円も増え、回転期間は3.72ヶ月となりました。これをどうみるのでしょうか。
売上の増加に比較して、売掛金の増加が著しいとき、相当の確率で資金繰りが悪化します。
一つは、これから支払う買掛金が増えているケースで、得意先の信用悪化から貸し倒れが起き、当社も資金繰りに行き詰まるケースです。
もう一つは、買掛金が増えていないケースで、この場合は、C興産やEセンターの決算日後の売上が、前倒しに売上計上されている粉飾決算のケースです。
売掛金は、このように内訳書から量的あるいは質的に分析することができ、熟練した金融マンは簡単な質問で見破ってしまいます。
◎ポイント
□ 内訳書で売掛金の残高が数年変わらなければ、回収不能として査定される
□ 売上の増加に比べて売掛金の増加が著しいときは要注意